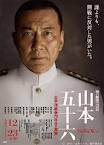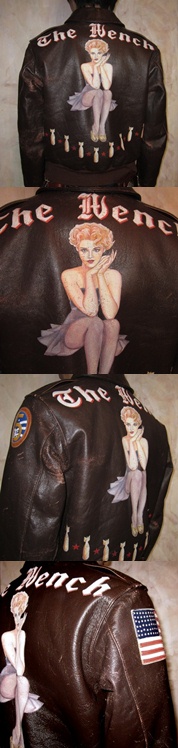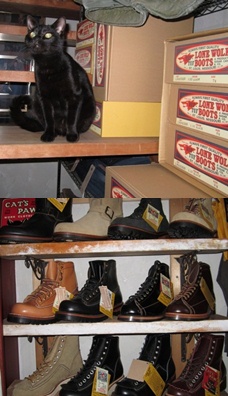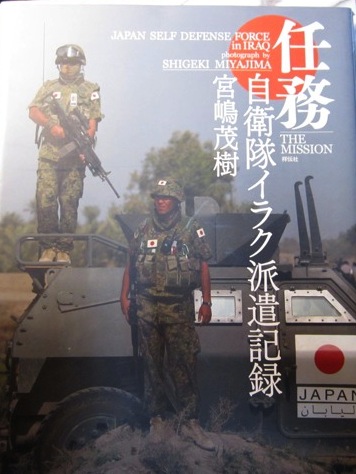今日はこんなイレギュラーな仕事も…。
ゴルフバッグの袋部分を留めるスナップ釦の修理依頼。
現物合わせで同じ規格のものがあったので打ち直しました。補強のため革でワッシャーをつくり、はさみこんで固定。
そういえばこの類の仕事では、トラックのトノカバーのスナップを全部打ちかえたことがありました。
☆☆☆ お知らせ ☆☆☆
1月31日(火)より2月14(火)まで店内改装のため、実店舗はお休みを頂きます。
その間WEBショップのほうは通常営業いたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
ゴルフバッグの袋部分を留めるスナップ釦の修理依頼。
現物合わせで同じ規格のものがあったので打ち直しました。補強のため革でワッシャーをつくり、はさみこんで固定。
そういえばこの類の仕事では、トラックのトノカバーのスナップを全部打ちかえたことがありました。
☆☆☆ お知らせ ☆☆☆
1月31日(火)より2月14(火)まで店内改装のため、実店舗はお休みを頂きます。
その間WEBショップのほうは通常営業いたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。